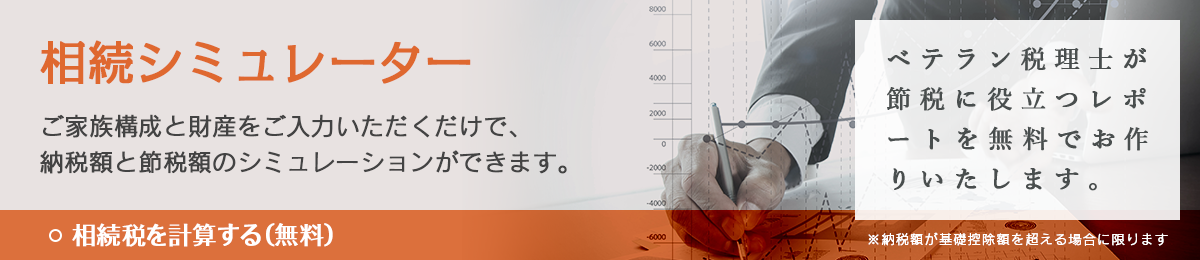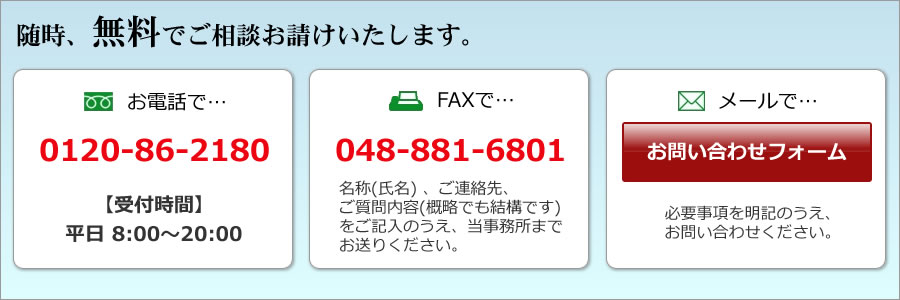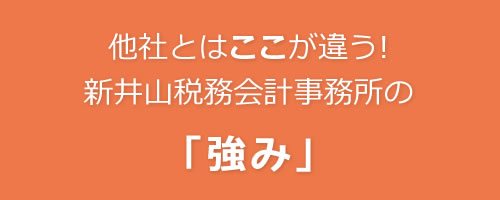<欠格事由>
相続で優位になるために罪を犯したり、被相続人を恐喝などして自分に有利な遺言を書かせたりすることはあってはならないことです。これらは欠格事由に該当し、相続権を失います。欠格事由に該当するのは次の場合です。
①故意に被相続人、先順位の相続人を殺害した者、または殺害しようとし刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたのを知っていながら告発、告訴しなかった者(ただし判断能力が無い者や、殺害者が配偶者または直系尊属の場合は除く)
③詐欺や脅迫により被相続人の遺言を妨害した者
④遺言書を偽造、破棄、隠匿した者
①については「故意」に殺害しようとした場合というのがポイントで、過失によって結果として殺人を犯してしまった場合や正当防衛が成立する場合な どは除外されます。④の場合も、あくまで相続で不当な利益を手に入れようとする者を対象としており、過って遺言を処分してしまった場合などは含まれませ ん。
欠格事由に該当する者がいる場合は、相続登記や名義変更などの相続手続きするために、確定判決の謄本や、その相続人が欠格事由に該当することの証明書などが必要となります。
<相続廃除>
欠格事由まではいかないものの、金をせびったり暴力を振るったりする相続人に相続させたくないというようなこともあるでしょう。被相続人の申請に より、家庭裁判所は相続人の相続権を失わさせることが可能です。これを相続排除といいます。相続排除ができるのは次の場合です。
①被相続人に対して虐待を加えたり、重大な侮辱をした場合
②相続人が著しい非行を犯したとき
ただし、被相続人の意思だけで排除ができるわけではありません。家庭裁判所へ排除の申請をし、認められてはじめて排除ができます。被相続人が「暴 力を振るわれた、金をせびられた」と申し出ても、家庭裁判所の調査で、被相続人にも非があるということが明らかになれば、排除は認められません。また、た とえ相続人と被相続人で相続排除についての合意があったとしても、家庭裁判所は職権で事実関係を調査することができます。あくまで排除の決定権は家庭裁判 所にあるのです。
排除は遺言でも可能です。この場合は被相続人に代わって、遺言執行者が家庭裁判所へ申請を出すことになります。遺言執行者とは、遺言による遺産分割を実行する人のことで、被相続人が遺言で指名するか、相続人の申し立てにより家庭裁判所が選任します。
請求の場合と同様に家庭裁判所に請求を出すか、遺言によって排除は取り消すことが可能です。取り消しの請求が真意であると認められた場合は裁判所は必ず取り消しを認めなければなりません。
尚、相続排除が認められた場合、相続権を失うのは該当する相続人だけです。子がいる場合は子が代襲相続します。