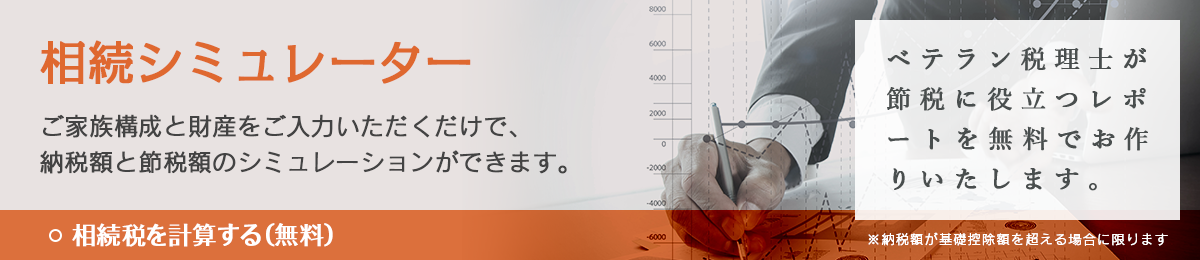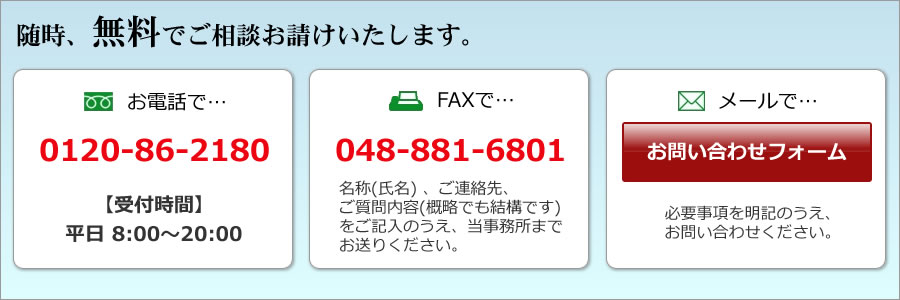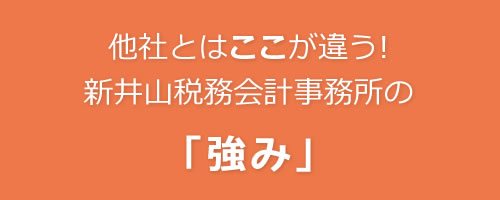相続税の対策
相続税の対策の種類は大きく分けて3つあります。
① 節税(評価を下げる)対策
節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる」方法です。
110万円を超えて贈与すると贈与税がかかり、一般的に相続税の税率より高率です。 しかし、その方法を工夫することで相続税より安く済ませることができます。 非課税枠を利用した贈与は期間が長ければ長いほど威力を発揮します。対策は 早め早めに実施することと理由の一つでもあります。
財産評価を下げる方法とは、土地であれば更地が一番高い評価となりますので、 遊休地をたとえばテナントを誘致し施設とともに利用してもらえれば、その土地の 評価はぐんと下がります。これはほんの一例にすぎませんが、あらゆる方策を巡らし 最善の対策を行うことは善良な納税者が行う権利であると思います。
② 争続(もめない)対策
どのように節税対策を行っていても相続を機に仲の良かった相続人たちで相続争いをしてしまっては、本末転倒になります。
まず、自身の財産をどのように分けていきたいのか、一番の有効策は「遺言書」だともいいます。さらに、財産を分けやすくするためにしておく準備を必要です。相続人の数だけ土地を分割することが必要なケースは往々にして見受けられます。
③ 納税資金対策
最後になりますが、これが一番大事な対策です。節税ばかりついつい気がとらわれがちですが、実際の相続税を納付する資金がなければ大変なことになります。
多額の現預金があればこの対策は必要ありませんが、多くの場合、そうではありません。納税は現金による場合のほか、延納、物納制度があります。これらの制度を理解し、またより有利に利用するための方策は多数存在します。死亡退職金、生命保険を含めて検討しましょう。
相続の手続き
本人死亡
↓
通夜・葬儀
↓
相続人選定
↓
相続放棄・限定承認の有無
↓
故人の準確定申告の提出と納税
↓
遺産調査
↓
相続税対象財産確認
↓
相続税評価額算定
↓
相続税申告書の提出と納税
以上の過程を10ヶ月のうちに対応しなければいけません。
相続が発生してからの対策では絶対に対応できないのがお分かりかと思います。
間違いない相続を今から準備し、実りある将来の繁栄を考えましょう。